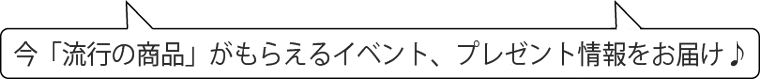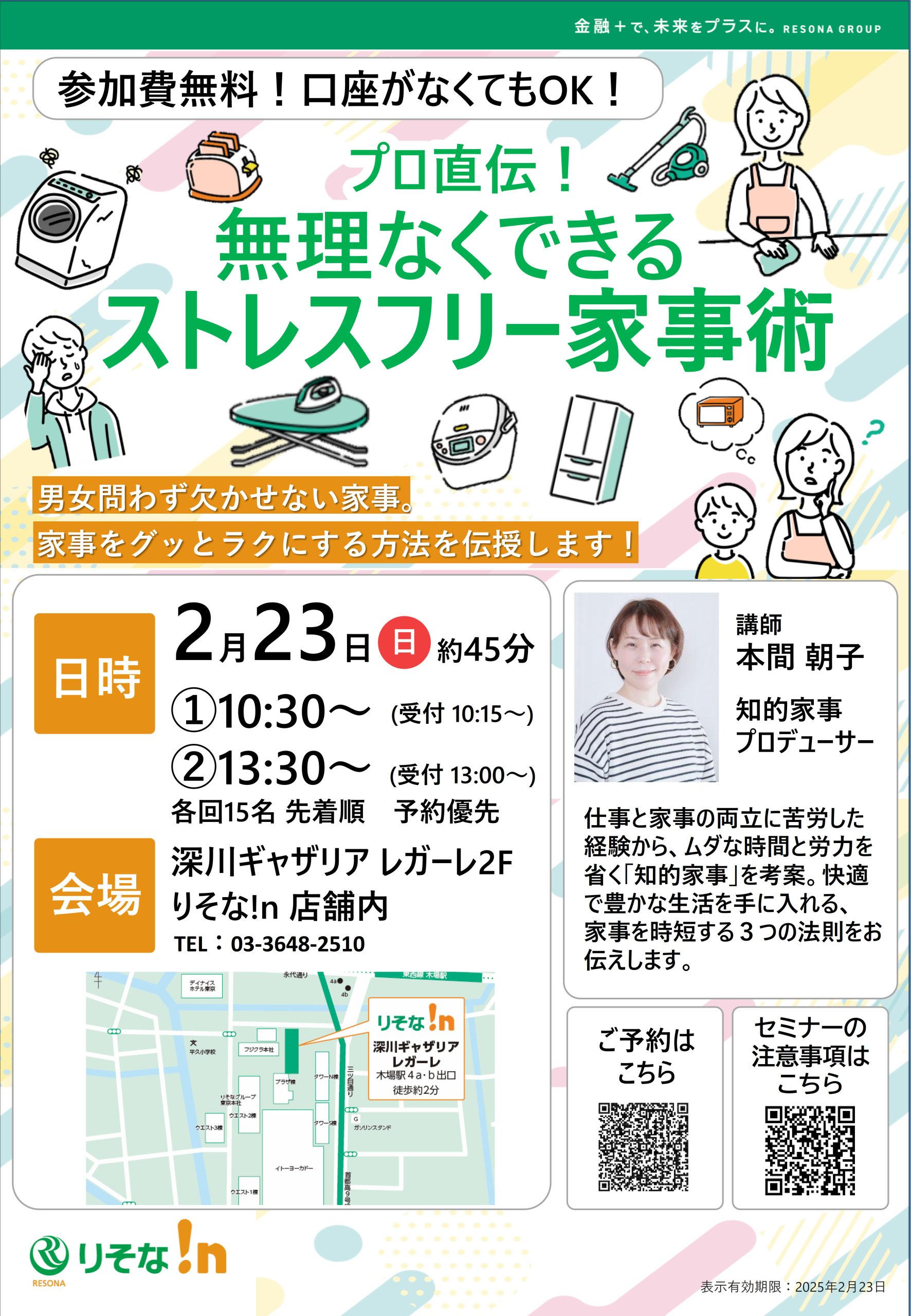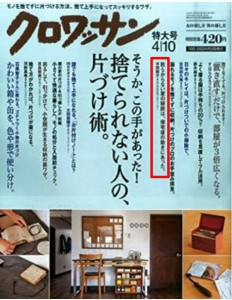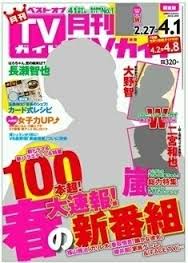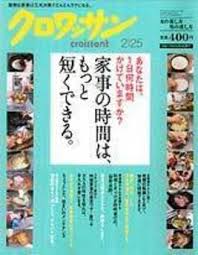・忙しくて家事をする時間や体力がない…
・家事を頑張っても誰も認めてくれずむなしい
・在宅ワークで家事の頻度が増えてつらい・・・
家事をしていて、そんな気持ちになったことはありませんか?
毎日家事をしていると、頑張ってもやる気が起きないこと、よくありますよね。
私たちは、人生のうちの「約2万時間」を家事に費やしていると言われます。
でも、それだけの時間を家事に使うのなら、
「もっと楽しく充実した時間にしたい!」
そう思いませんか?
そんな方にぴったりの「時短家事セミナー」を、2月23日(日)に無料開催いたします。
講師:本間朝子(知的家事プロデューサー)
内容:
●効率的な掃除の方法
●時短料理のコツ
●予防家事で家事をやめる など
家事の悩みを解消し、もっと楽しい毎日を送りましょう♪
当日、会場でお目にかかれることを楽しみにしております!
詳細・お申込み👇
日時:2025年2月23日(日)
①10時30分〜 約45分
②13時30分〜 約45分
●各回15名 先着順 予約優先
場所:深川ギャザリア レガーレ2F りそな in 店舗内(東西線 木場駅 徒歩5分)
お申込:コチラ からお願いいたします。
※予約の反映にお時間がかかる場合がございます。